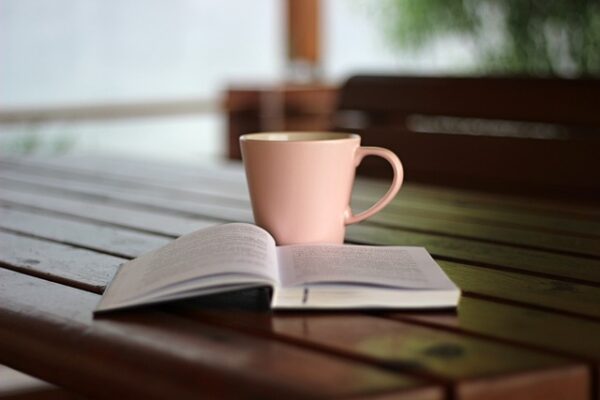
統合報告書アワード2024-2025
今年も統合報告書のアワード/ランキング結果が各社から発表されて揃いましたのでシェアします。
毎年、年末・年度末に発表される統合報告書のアワードですが、主要なものは本記事で紹介する3つです。最近は新しいアワードも行われませんので、この数年で3つに集約されています。それぞれ特徴があるので、良い悪いというものではないのですが、評価項目や評価コメントなどは非常に参考になるものばかりです。ぜひチェックして、統合報告書の制作のヒントにしていただければと思います。
WICI統合リポート・アウォード2024
■Gold Award(優秀企業賞)
伊藤忠商事、TDK、野村総合研究所
■Silver Award(優良企業賞)
東京応化工業、ローム
■Bronze Award(準優良企業賞)
MS&ADインシュアランスグループホールディングス、塩野義製薬
■Special Award(審査員特別賞)
イトーキ
出所:https://wici-global.com/index_ja/2024/12/02/4534/(2024年12月発表)
第4回日経統合報告書アワード
■総合グランプリ
デンソー、日本ペイントホールディングス、丸紅
■準グランプリ
旭化成、伊藤忠商事、イトーキ、SWCC、オリックス、富士通
■特別賞
グランプリE賞:積水化学工業
グランプリS賞:しずおかフィナンシャルグループ、積水ハウス
グランプリG賞:栗田工業
■優秀賞
アシックス、アステラス製薬、石原産業、ANAホールディングス、SCSK、NTTデータグループ、大塚ホールディングス、オムロン、花王、カナデビア、兼松、キリンホールディングス、クボタ、KDDI、小松製作所、Sansan、参天製薬、住友化学、住友ゴム工業、セイコーエプソン、ソフトバンク、大成建設、大和証券グループ本社、TDK、ディップ、東急不動産ホールディングス、東京応化工業、戸田建設、ニチレイ、野村総合研究所、パーソルホールディングス、日立製作所、富士フイルムホールディングス、本田技研工業、三菱商事、三井住友トラストグループ、三井物産、三井不動産、三越伊勢丹ホールディングス、三菱重工業、ミネベアミツミ、村田製作所、ゆうちょ銀行、横浜ゴム、リゾートトラスト、レゾナック・ホールディングス
出所:https://ps.nikkei.com/nira/result24.html(2025年3月発表)
GPIFの国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」
4機関以上:伊藤忠商事、野村総合研究所、日立製作所、ソニーグループ、味の素、積水ハウス、荏原製作所、三菱UFJフィナンシャル・グループ
3機関:アサヒグループホールディングス 、コンコルディア・フィナンシャルグループ、三井物産
2機関:INPEX、双日、旭化成、レゾナックホールディングス、積水化学工業、富士フイルムホールディングス、AGC、オムロン、日本電気、ウシオ電機、NISSHA、アシックス、東京エレクトロン、第一生命ホールディングス、東京海上ホールディングス、九州電力
※複数の運用機関に評価された企業を抽出
出所:https://www.gpif.go.jp/esg-stw/20250311_integration_report.pdf(2025年3月発表)
追記:日興リサーチセンター「Integrated Report Award 2025」
◯ベストプラクティス賞
日本ペイントホールディングス、ジーエスユアサコーポレーション、シスメックス、SCREENホールディングス
◯優秀賞:財務部門
大和ハウス工業、TIS、ローム
◯優秀賞:非財務部門
ニデック
出所:投資家視点での統合報告書の評価結果~2024年度~(2025年6月発表)
投資家視点のフィードバック
GPIFの資料で「日本企業が作成する統合報告書、または日本企業の情報開示全般に対する期待や改善してほしい事項」について、運用受託機関からのコメントとして掲載しているのでその一部を紹介します。統合報告書の制作を行なっているすべての企業と制作会社はチェックすべきです。
適切なマテリアリティを設定し、事業を通じた課題解決により経済価値と社会価値を創出する経路に、資本の強みや独自のビジネスモデルを明確に示すことで、解像度高くプロセスが理解できるような記載をお願いしたい
短・中期戦略において重要なESG課題を明示し、定量的なKPIを設定していること(ESGが事業に真に統合されていることを示すもの)
ステークホルダー・エンゲージメントには、投資家を含めること、ESGの議論の証拠が示されていること
持続的な成長や価値創造に資する観点でのマテリアリティに準じた情報開示と、定量的な指標に基づく目標と進捗の開示。
トップからのメッセージは長期的な視点で企業のありたい姿を語って欲しい。
開示はかなり進んでいる。ただ、規定演技を美しく見せることに注力しており、事業との関連性を説明できている企業は少数である。再度、なぜ非財務を開示する要請が投資家からあるのかを考えてほしい。
統合報告書はマテリアリティ(マップ・特定プロセス)を記載することが目的ではなく、マテリアル(重要な)情報を記載するものであり、記載されているからには経営上重要な情報である(=経営が当然認識・考慮している)ことが重要と考える。
統合報告書のページ数が増えるなかで、各事業に同じページ数を割くのではなく、よりステークホルダーの関心事項に焦点を当てることが重要。その他オンライン媒体を上手く活かし、統合報告書ではその年度のよりマテリアルな点に絞り、メリハリを持った内容であることが望ましい。
出所:https://www.gpif.go.jp/esg-stw/20250311_integration_report.pdf
受賞企業比較

上記3つの上位評価企業を表にしてみました。3つのアワードで高評価を得たのは伊藤忠商事のみです。2社のアワードを受賞する企業もいくつかありますが、数社程度です。評価項目や方針が異なるので、その中で高評価を得ているのは素晴らしいと思います。今期でいえば、伊藤忠商事、野村総合研究所、積水ハウス、イトーキ、の4社あたりが総合的高評価企業と言えるでしょうか。全受賞企業を比較してもいいですし、色々な角度から分析してみてください。
所感
たとえば、日経統合報告書アワードでは、主要評価項目を公開しています。人間がチェックしているのでブレはありそうですが、開示すべき指標として参考になります。WICIの評価項目の話も聞いたのですが(当社WICI会員です)、IFRS財団のIRフレームワークの要素も多く含まれるようです。
極端ですが、日経とWICIの評価項目と、GPIF評価の評価コメントと、IRフレームワークの推奨開示項目とを合わせれば「私の考えた最強の統合報告書」が出来上がるはず。自称コンサルタントの適当なアドバイスを聞くよりも、まずはこのあたりのコンテンツや開示方法の整理をするとよいでしょう。
あとは、投資家サイドの方の話を聞くと、結局、統合報告書はコミュニケーションツールなので、統合報告書を使っていかにステークホルダー(主に投資家)とコミュニケーションをしていくかがポイントであり、コンテンツ制作そのものに時間をかけすぎても意味がない、という話も聞きます。
他には、毎年、これらのアワードの受賞企業が変わり映えしないこともよく指摘されますが、評価項目が大きく変わらない以上、大きな入れ替わりは今後もないのでしょう。私は、評価項目の変更は必ずしもする必要はないと思っていますが、審査員が同じなのは気になりますね。評価サイドのガバナンスというか、長期で審査員をしていれてば癒着が起きる可能性もありますし、人間なので何らかの接点があれば、意図せずに好意的評価をしてしまう可能性もあります。
プライム企業でも、時価総額の小さい企業の統合報告書は読まれない(必要ない)とも聞きますが、中小規模の上場企業こそ、統合報告書で独自性を追求し、自社への共感や理解を求めるべきだとは思っています。
まとめ
統合報告書のアワード/ランキング、およびその評価についてまとめました。
有価証券報告書でのサステナビリティ開示(SSBJ基準)が「サステナビリティ関連“財務”開示」と言われ、統合報告書も同一企業の開示物として整合性や一貫性が求められるため、有報とのコンテンツの統合というか、マテリアルな情報の一貫性はより重要になってくるでしょう。
上記の結果やコメント等を参考に統合報告書制作に今年もチャレンジしてみてください。私も統合報告書制作における第三者意見をよくさせていただいているので、上記内容を研究して自身の精度を高めていこうと思いました。
関連記事
・サステナビリティ推進におけるインパクト評価(効果測定)の課題
・統合報告書におけるトップメッセージの考え方
・統合報告書の中身が思いつかない担当者様へ